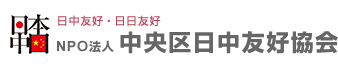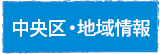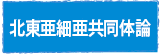北東亜細亜共同体論
米価高騰問題を先物市場で考える (2025.03.15)
米価高騰問題を先物市場で考える
いまのコメ価格の暴騰が、今後どうなるか。それを先物市場での実際の取引の事実を見て、考えよう
さて、先物市場だが、「先物買いのゼニ失い」と言って、先物を話題にすると、眉を顰める人」がいる。
だが、神谷慶治先生は違っていた。ある時、「農村での講演会で先物の話をすると、一瞬だが会場が静かになる」と言われたことがある。
このことを、聞いていた我々学生は、先物市場の勉強しておきなさい、という教えと忖度していた。
. ◇
さて、本題のコメの先物市場である。
コメの先物市場は、昨年8月に認可されたばかりで、まだ取引量も少なく、将来のコメ価格を予測する資料としては、必ずしも十分なものではない。しかし、ここで将来予測を誤れば、実際に金銭の損失を被る。そうした事実に基づく、いわば真剣勝負の結果の資料である。
ここでは、業界用語を多用する。だが、それは煩雑なので、そのつど括弧()で説明しよう。
.

上の図は、コメの先物市場として、日本で唯1つの市場である大阪の堂島取引所の資料によって、先物価格を図にしたものである。
これは、コメの先物価格で、今年の6月限(ロクガツギリ)の先物価格である。つまり、今年の6月末に「実際に現物のコメを売買する約束」を売買する価格である。
今年6月末の現物価格が、いまの先物価格より高くなれば、先物を買った人は利益が得られる。だが反対に、安くなれば、損失を被る。高くなる、と予想して、買う人が多くなれば、先物価格は高くなる。だが反対に、安くなる、と予想して、売る人が多くなれば、先物価格は安くなる。
そのつどぜり合いで、買う人の数と売る人の数が同じになるまでセリを続ける。 それが、セリの結果の価格が、先物価格である。
この先物取引は、今年の6月限のばあい、今年の6月末まで、毎日行われる。そして、それが先物価格である。上の図は、その日の最後の取引で決まった先物価格である。
. ◇
さて、前置きが多くなったが、上の図を詳しく見てみよう。
ここで示した先物価格は、8月13日に先物取引が認可されたのだが、認可された直後から先週末までのものである。
直後の未熟さはあるが、売買者が、いわば人生を賭けた貴重な結果である。
ここで、今年の6月限を選んだ理由は、今年のコメの端境期の米価をどう予測するか、である。くり返すが、関係者の生命を賭けた予測である。根拠も薄弱で、天井を睨んで行った予測ではない。
. ◇
(追記)
先物市場の資料ではなくて、現物市場の資料もある。今後、米価が高くなると予想する人は、実際にコメを買いだめておくのだが、品質を劣化させないために、温度と湿度を適正に管理しなければならない。しかも、価格を公表するのが、月に1回程度で、しかも遅い。だから、対策が遅れる。
それよりも、先物市場の資料は、毎日の夕方に、ネットで、その日の資料が公表される。だから、早く対策ができる。
これが、本稿で先物市場の資料を使った理由である。
. (2025.03.17 JAcom から転載)