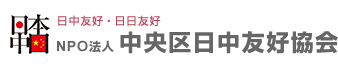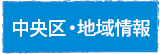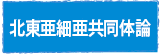北東亜細亜共同体論
二重米価制で農業者の政治不信を一掃せよ (2025.04.20)
二重米価制で農業者の政治不信を一掃せよ
政府は米価高騰の対策として、相変わらず拙劣な「兵力の逐次投入」を続けている。備蓄米を少量づつ放出する、という戦術である。だから米価は下げられない。「兵力の逐次投入」の見本である。
今週も放出し、今後も毎月少量づつ放出するのだという。そろそろ備蓄米がゼロになる日は近い。その後はどうなるのか。兵力がゼロになる日が、不気味に迫っている。このままでは、新米が出回る前には、備蓄米は底をつくだろう。その後に打つ手段があるのか。
先週、政府は、財政審を隠れ蓑にし、どさくさに紛れて加工用のMA米を主食用にして、急場を凌ごうとしていることが分かった。このMA米は、政府が1993年に「断腸の思い」でアメリカと約束し、だが、大部分は加工用にすることを、農業者に誓ったものである。農業者は「満腔の怒り」を込めて抗議したが、押し切られた。
政府はいま、この誓いを破ろうとしている。農業者の政治不信は頂点に達し、怒髪は天を衝いている。
政府が約束を破って、加工用のMA米を主食用にしたいのなら、生産者に生産費を補償する二重米価制を法制化した後で考えるべきだろう。そうすれば、農業者は黙認するかもしれない。
どうして、こんなみじめな農政が続いているのか。
ここには、米価を下げるには供給量を増やすしかない、という経済思想が唯一つの正しい経済思想だ、という考えがある。だが、それは市場原理主義という反国民的で偏狭な、1つの経済思想に過ぎない。偏屈な国家経営の信念でもある。
. ◇
そもそも経済とは何か。それは、誰が何をどれだけ生産し、誰が何をどれだけ消費するか、を決める社会組織である。このさい、市場価格は潤滑油の役割りしかない。
政府は、そうした端役の価格を格上げし、主役にして、露出させている。だから、価格が舞台=市場の真ん中にしゃしゃり出て、市場を支配している。これが市場原理主義であり、この農政版が市場原理主義農政である。
こうした農政が、いま市場の動乱を招いているのである。
これに代わるべき経済思想は何か。
. ◇
本ホームページで、長い間、論陣を張った、今は亡き2人の大先生は、かつて何を言ったか。
宇沢弘文先生は、農業は社会共通資本だ、と言った。道路と同じように、市場で決めるのではなく、社会の責任で、それを委託された政治の責任で、社会へ無料で、あるいは低廉で供給すべきだ、と言った。
また、内橋克人先生は、FECといって、食糧とエネルギーと医療・介護は、全ての国民が充分に享受できるように、市場で決めるのではなく、社会の責任で、それを委託された政治の責任で、無料で、あるいは低廉で供給すべきだ、と言った。
もちろん、両先生とも、生産費は政治が補償する。つまり、二重米価制の提言である。
いまこそ、この両先生の経済思想を生かすときではないか。だが、この思想を受け継ぐ学者は、いないようだ。すくなくとも、政府の近辺にはいない。国民の、ことに農業者の政治不信は、ここに発している。
. ◇
前置きが、長くなったが、本題へ入ろう。いまの米価高騰が農業者に何をもたらしているか。
農業者は、言うまでもないことだが、米価で生産費を償えなければ、生産を続けられない。脱農するしかない。そしていま、その危機にある。
どうするか。
二重米価制を採用し、生産者米価と消費者米価を別々にして、生産者の手取金額を補償することで脱農をくい止めるしかない。ここでは、生産者米価は市場価格ではなく、市場価格に政治が交付する補償金を加えた農家手取り単価とする。以下では、この補償米価を推計しよう。
いま、米価高騰といっているが、それは再生産ができるような米価かどうか。脱農を止められるほどの高騰か、ということが問われている。
. ◇
ここで、再生産ができる価格を生産者の補償米価としよう。そして、その補償米価を推計しよう。
どれほどの補償米価なら生産費が補償されるか。そして、脱農を食い止められるか。
生産費は、農家によって、それぞれ違う。その平均を補償米価すればいい、という訳ではない。それでは、半数しか生産費を償えない。そうなれば、再生産が可能になるのは半数しかない。残りの半数は再生産が不可能になって脱農する。そうなれば、生産量は半減する。その結果は、食糧自給率の激減であり、食糧安保の危機の深化である。
そこで、生産費の分布を見てみよう。下の図がそれである。
これは、2022年産米についてのものである。横軸は生産費で、縦軸はその生産費以下で生産している生産量の割合である。
しばらくの間、2022年産米について考えよう。2024年産米は、まだ販売の途中で資料が揃っていないからである。
さて、90%のコメが生産費を償う米価を補償米価としよう。そうすると、この図で示したように、玄米60kg当たり、2万2、659円になる。これが、生産者米価の2022年産米の補償米価である。90%でなく95%なら、もっと高くなるのだが、ここでは、90%とする。
これに対して、同じ資料で2022年産米の農家庭先価格をみると、9、907円である。
これらを今年2月の時点に更新しよう。
. ◇
はじめに、補償米価を更新しよう。2022年産米の生産費を基にして、2024産米の生産費を、最近の資料から推計する。「農業物価統計」と「毎月勤労統計」による米の生産費のインフレーターの1.026971を掛け算すると、玄米60kg当たり23270円になる。これが、生産者の補償米価である。
つぎに、農家庭先価格である。まだ、販売中だが、今年2月の資料で推計しよう。いま、卸売米価も小売米価も2倍になったのだから、農家庭先価格も2倍になるとして推計しよう。そうすると、1万9、814円(9907X2)になる。これが現時点の農家庭先価格になる。
この差が補償金になる。つまり、補償金は3、456円(23270―19814)になる。だから農業者は、市場から1万8、914円を販売代金として受け取り、政府から3、456を円補償金として受け取って、生産費の2万3、270円を償うのである。
. ◇
このときの、政府の補償金総額を計算しよう。
補償の単価は、玄米60kg当たり3、456円だから、1kgでは57.6円、1トンで5万7600円、1万トンで5億4、760万円になる。補償の対象は、消費仕向けの702万トンだから、補償総額は、3、844億円(54760X702)である。
これを多くの人は、少額とみるに違いない。だが安心してはいられない。今後、販売価格が下がれば、補償金が増える。
政府は、このような二重米価制を決断できるか、どうか。3か月後の参院選を前に、多くの国民が注目している。与野党の論戦を期待している。
.
.
【余談】特米(トクベイ)のはなし
特米とは、業界用語である「特定米穀」の略語である。いまは「ふるい下米」というようで、その名の通りである。精米のときに、糠とともに発生する、主に砕米である。
トクベイと発音する。濁音があるので威勢がいい。雑踏の中でもよく響く。しかし、上品な人は、濁音があるので、唾が飛ぶようで汚らしい、と顔を顰める人もいるだろう。
用途は、味噌などの加工用で、だから価格は正規のコメよりも格段に安い。
この特米を、最近よく見るようになった。筆者の行きつけのファミレスの、ご飯の中にも混じるようになった。コスト削減の知恵なのだろう。安価だけでなく、食味もわるくない。だが、水っぽいという難点がある。理由は、炊飯器にあるのだろう。
以前、業界調査のときに教わったのだが、炊飯器には温度曲線というものがある。「初めトロトロ中パッパ」というご飯の炊き方を学術的に表現したもので、横軸を時間、縦軸を温度にしたグラフの曲線のことである。この曲線を炊飯器に教えておけば、美味いご飯が炊ける。
インディカ米は砕米の混入率が5%というのが標準米である。15%というのもある。だから、砕米を美味しくたべる工夫がある。インディカ米にはインディカ米温度曲線がある。それを、炊飯器に教えておけばいい。ジャポニカ米用の炊飯器の温度曲線とは違う。
ファミレスの担当の方は、いちど東南アジアへ行って、現場を見てきたらどうだろうか。改善の余地があるだろう。そして、いまの難局を乗り切る一助になるだろう。
そして、その先に、食糧を公共財とする二重米価制を展望しよう。
. (2025.04.21 JAcom から転載)