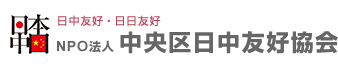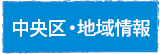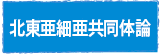北東亜細亜共同体論
備蓄米放出で先物米価は8%下げ・・・大局観の欠如 (2025.03.31)
備蓄米放出で先物米価は8%下げ・・・大局観の欠如
備蓄米放出の効果を先物市場でみてみよう(文末の注参照)。
最近の先物価格をみると、下の図で示したように、先週末の先物価格は、直近のピーク時と比べて僅かに8%下げただけである。ここには、政府の米政策に対して、多くの国民が持っている、抜き難い不信がある。それを、先物市場が反映したのだろう。
この不信の底には、政府のコメ政策における大局観の欠如がある。政府は、いったい本気で米価を下げようとしているのだろうか。
. ◇
米価が上がったままでは、あるいは、少しくらい下げても、消費者のコメ離れは、止まらないだろう。コメからメンやパンへ代わっていくだろう。その結果、コメの需要量が減り、輸入小麦が増えることで、食糧自給率が下がり、食糧安保に危機がやってくる。
また、少しでも下げれば、生産農家の離農が加速するだろう。その結果、コメの供給量が減り、食糧自給率が下がり、食糧安保に危機がやってくる。
上げてもダメ、下げてもダメ、という状況のもとで、政治は立往生している。国民は、政治不信を募らせている。
. ◇
だから、政府が、備蓄米を放出すると言っても、国民は、その結果、米価が下がるとは思えない。そのことを、先物市場は見透している。
アナウンスメント効果は全くないのである。日銀の為替市場介入のときの、アナウンスメント効果とは、雲泥の差がある。
そうして、実際に放出しても、先物米価は、それほど下がらない。
なぜ、こうした無残なことにしてしまったのか。それは、政府がコメ政策に大局観を持っていないからである。

上の図は、コメの先物市場で、先物価格をみたものである。コメの端境期になる、今年の6月限の先物について、昨年の夏から先週末までの先物価格を、それぞれ、営業日の終値で示した。詳しく見よう。
最近の2月26日には2万8,330円(玄米60kg当たり)だった。これは、政府が備蓄米放出の入札日を3月10日にすることを発表した3月3日の直前だった。先物市場が放出を催促したものだろう。
それ以後、先物価格は下がったものの、3月18日には下げ止まった。僅か9%の下落だった。
その後、横這いを続け、先週末は8%の下げに止まっている。
これで消費者のコメ離れを止めようとしても、とうてい無理だろう。
. ◇
ここには、政府のコメ政策に対する不信感が、如実に表れている。
つまり政府が、備蓄米を僅かばかり放出するとアナウンスしても、先物米価は、ほとんど下がらなかった。入札後も、ほとんど下がらなかった。ようやく今週中には、小売店の店頭に並ぶようだが、小売米価も、ほとんど下がらないことを、先物市場は予想しているのだろう。
なぜ、こんなことになってしまったのか。
. ◇
政府のコメ政策に、大局観が見えないことが、不信感の底にある。
大局観が見えないのは、大局観が無いからである。無いものは見えない。見えるとすれば、それは幻である。
もう少し正確に言おう。
政府には、うすぼんやりした大局観が2つある。
1つは、大企業中心の財界の理念に忖度した、市場原理主義農政である。この農政の帰着するところは、食糧安保の無視である。
もう1つは、政治の市場介入による、食糧安保の重視である。ここには、政治の決断による財政資金の投入が、不可欠になる。この点でも、財界を横目にして、尻込みをしている。
政府は、この2つの大局観のなかで、揺れ動いている。
.
3か月後には参院選がある。コメ政策は、重要な争点になるだろう。チマチマした論争は要らない。大局の論争を期待しよう。
.
.
【注】 日本のコメ先物市場は、昨年8月に再開したばかりで、まだ取引量が少なく、必ずしも十分な資料ではない。しかし、第一級の資料である。
. (2025.03.31 JAcom から転載)